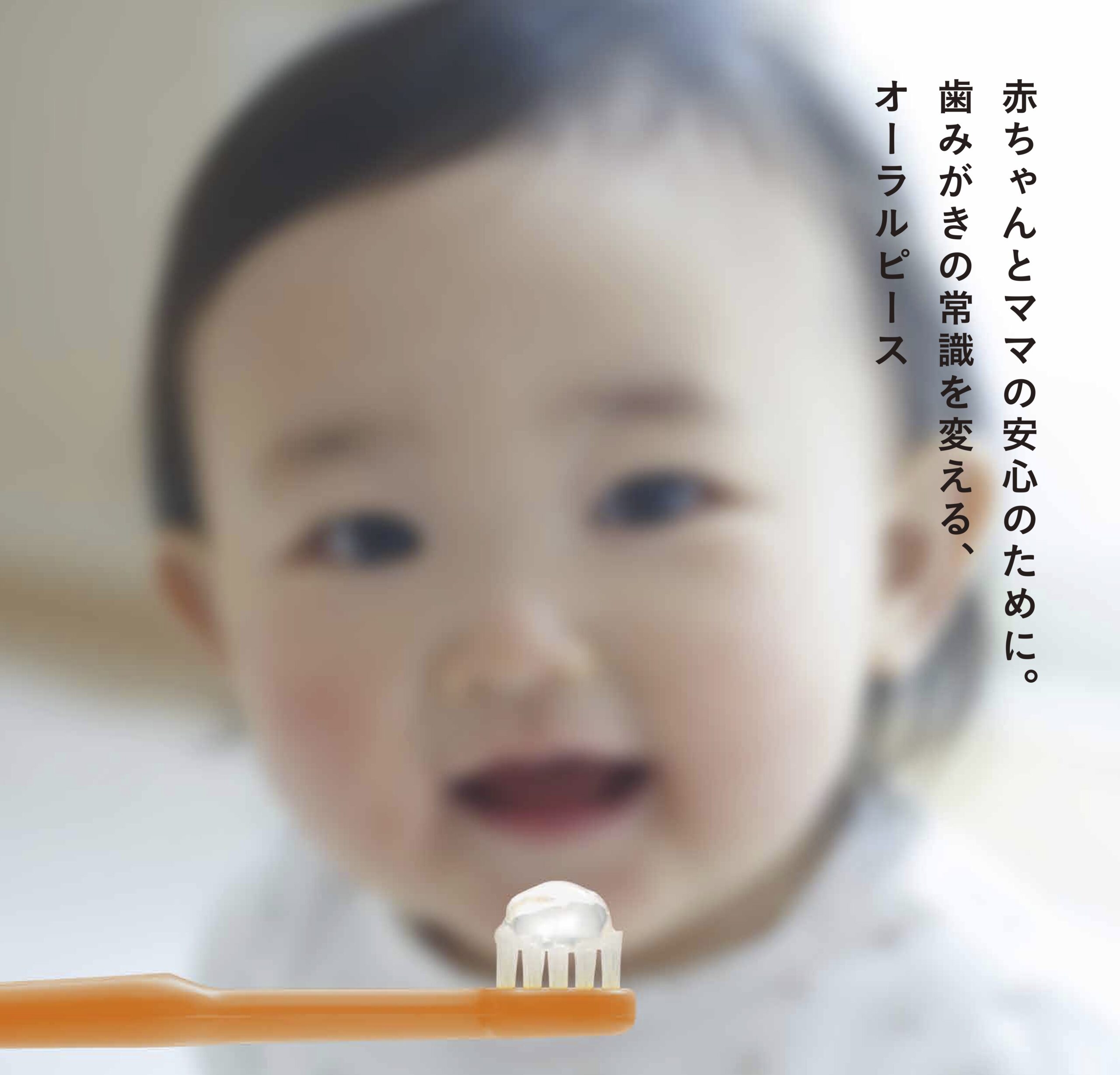
これまで歴史的に人類が食べてきた物にもフッ素は含まれるが安全濃度
フッ素は自然界に広く分布しており、多いもので紅茶や海藻、微量で日本茶(緑茶)、以下ごく微量で他の食品にも含まれています。
塩やお茶、食品、さらには人体にも自然界由来のフッ素が含まれており、「フッ化物はまったく安全だ」と主張する人もいます。また、「塩も濃度によっては毒になるのだから、フッ素も適量であれば安全だ」という意見もあります。しかし、歯磨き粉や洗口液に含まれるフッ素の濃度は、生き物が生息可能な自然界の濃度の約1,000倍にも及びます。そのため、塩などと比較しても、フッ素濃度における暴露レベルはまったく異なる話なのです。
また、虫歯予防の無機フッ素化物などのフッ素化物は、植物や生物、海水等の自然界から集めてつくり出す技術はなく、高濃度のフッ素を含む鉱物である蛍石(フロライト)から精製される化学物質で、そのフッ素濃度レベルが自然界の植物や生物から作られる食品とは全く違います。
| 食品 | フッ素濃度 (mg/L, ppm) |
|---|---|
| 紅茶 | 1.0~4.0 |
| 海藻 | 0.5~2.0 |
| 魚 | 0.2~2.0 |
| 緑茶 | 0.1~0.6 |
| 野菜 | 0.05~0.5 |
| 味噌 | 0.1~0.5 |
| 塩 | 0.01~0.2 |
| 肉 | 0.01~0.1 |
| 果物 | 0.01~0.1 |
食品でフッ素濃度が高いものは紅茶です。お茶の葉には、主成分である覚醒作用があり集中力を高める「カフェイン(200~400mg/L(200~400ppm))」以外に、産地によって土壌や水から吸収されたフッ素が含まれており、濃度が高い場合があります。
紅茶:1.0~4.0mg/L(1.0~4.0ppm、紅茶は土壌フッ素量の多いインド産が多い、濃い紅茶ではさらに高くなる場合がある)
日本茶(緑茶):0.3~0.6 mg/L(0.3~0.6ppm、通常の抽出濃度)
コーヒー:0.1~0.6 mg/L(0.1~0.6ppm、通常の抽出濃度)
海藻はフッ素を含む海水中(約1.3ppm)の成分を吸収するため、比較的多く含まれています。
魚は骨ごと摂取の場合は高濃度となり、骨や魚卵に多く含まれる傾向があります。
赤ちゃんや子供、妊活中や妊婦さん、授乳中のママは、アルコールやカフェイン、コーヒーや緑茶を何リットルも、濃い紅茶を何杯も、魚の骨や昆布、味噌や塩を何キロも、飲み過ぎ食べ過ぎに注意が必要です。
ただ、歴史的に人類が食べてきた自然の食べ物からのフッ素暴露量は、普通の食事量であれば安全で、高濃度フッ素汚染地域以外の生物や植物に含まれる自然界の微量のフッ素摂取は歴史的にも生物や植物、人類に安全といえます。
一方、高濃度フッ素暴露は「歯磨き粉の方が暴露リスクや量が桁違いに高い」と指摘されています。
一度で1,000倍以上の高濃度フッ素暴露リスク 1ppm程の水道水や食品より1,000ppm以上の歯磨き粉や洗口液の方が桁違いに摂取量を高める 経皮吸収にも注意
アメリカのフッ素を添加した水道水のフッ素濃度(一般的に0.7~1.5 ppm)や緑茶(一般的に0.3~0.6 ppm)と比べると、歯磨き粉などで1,000ppm以上の高濃度フッ素を含む製品の誤飲や経皮吸収は、フッ素暴露リスクが大幅に高いと言えます。以下の点がその理由です。
1. フッ素濃度の違い
水道水中のフッ素濃度は0.7~1.5 ppmと非常に低く、飲料水として摂取される際、少量のフッ素が徐々に体内に入るレベルです。そして2〜3リットル以上の水も一度には飲むことができず、フッ素濃度が劇的に増えることは少なく安心です。
一方、歯磨き粉のフッ素濃度は通常100ppm以上で、大人用では1,500ppmに達することもあります。このため、歯磨き粉を口に残す、または間違ってほんの一部を誤飲するだけでも、一度のミスの摂取量で水道水の数100~数1,000倍となり得ます。
2. 吐き出しても残るリスク
歯磨き粉は、通常の使用でも口内に残留しやすく、特に子供や乳幼児は完全に吐き出すことが難しいため、フッ素が唾液と混じり吸収されるリスクが高まります。
経皮毒の観点から、口腔粘膜は腕などの皮膚の10~20倍の吸収率があるため、微量でも口腔内にフッ素が残ると高い吸収率で体内に取り込まれやすくなります。
フッ素が体内に取り込まれるリスクは、濃度が高く吸収率の高い歯磨き粉や洗口液の使用による経口暴露・経皮吸収の方が、日常的に飲用するフッ素添加の水道水に比べてはるかに高いと言えます。そのため、特に乳幼児や子供向けの高濃度フッ素製品の使用には慎重な配慮が必要です。
過去の世界保健機関(WHO)による高濃度フッ素配合製品の誤飲防止指導
世界保健機関(WHO)は、2020年にフッ化物配合歯磨き粉の使用について以下のガイドラインを示しています。
フッ化物濃度: 歯磨き粉中のフッ化物濃度は、年齢に関係なく1,000~1,500 ppmが推奨されています。ただし、子供(特に6歳以下)の場合は、過剰摂取や誤飲防止のために使用量の管理と保護者の監督が重要としています。
- 3歳未満:米粒大(0.1 g)を使用し、誤飲防止を徹底。
- 3~6歳:豆粒大(0.25 g)を使用し、飲み込まないよう監督。
- 6歳以上・成人:1 gを適切に使用し、すすぎを最小限に。
これらの推奨事項は、2020年12月24日発表された、WHOの公式文書「Fluoride toothpaste 1. Summary statement of the proposal for inclusion」に記載されています。
過去のWHO基準での一回の歯磨きでのフッ素の体内摂取量(1,000 ppm〜1,450 ppm)仮定
| 年齢層 | 使用量 (g) | 飲み込む割合 | 1,000 ppm 製品の摂取量 (mg) | 1,450 ppm 製品の摂取量 (mg) |
|---|---|---|---|---|
| 3歳未満 | 0.1 | 50% | 0.05 | 0.0725 |
| 100% | 0.1 | 0.145 | ||
| 3~6歳 | 0.25 | 50% | 0.125 | 0.18125 |
| 100% | 0.25 | 0.3625 | ||
| 6歳以上・成人 | 1 | 10% | 0.1 | 0.145 |
| 100% | 1 | 1.45 |
以上の様に、2020年の世界保健機関(WHO)においても6歳未満の乳幼児のフッ素摂取には注意と監督を徹底する様に呼びかけています。また推奨する1日2回の歯磨きで妊婦であるママは、2024年の赤ちゃんへの最新リスク摂取量に近づく可能性もあり注意が必要です。
また世界保健機関(WHO)は、6歳未満の子供に対するフッ化物洗口を推奨していません。(WHOの1994年のテクニカルレポート「Fluorides and Oral Health」(Technical Report Series No. 846))
世界保健機関(WHO)では、乳幼児のフッ素暴露についての危険性から、3歳未満は米粒大を使用し誤飲防止を徹底、3~6歳は豆粒大を使用し飲み込まないよう監督と、ごく少量を使用しフッ素は「決して飲み込まない様」に指導しています。
さらにこのレポートでは、世界保健機関(WHO)が6歳未満の子供にフッ化物洗口を推奨しない理由として、誤飲リスクやフッ素症の懸念について述べています。
高濃度フッ素配合製品の濃度による暴露レベル
最新の判決では、水道水の場合でフッ素濃度0.7 ppm=0.00007%=0.7 mg/Lでの子供の脳への影響リスクが指摘しており、それ以上の高濃度フッ素が配合された歯磨き粉の一日の歯磨き回数と継続使用日数を考慮し、誤飲や経皮吸収による口腔粘膜からのフッ素摂取量による脳への影響リスクに気をつける必要があります。
フッ素配合製品の濃度によるリスクレベルを整理すると以下の通りです。判決によって認められたリスクを基にした基準を0.7 ppmすると、高濃度のフッ素が含まれる歯磨き粉は、誤飲や経皮吸収によるリスクが増加すると考えられます。
| 配合フッ素濃度 (ppm) | % 表記 | mg/L | リスクレベル(水道水の何倍か) | 同等リスク水道水量 | 製品1グラムあたりのフッ素量 (mg) | 製品0.1グラムあたりのフッ素量 (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 ppm | 0.00007% | 0.7 | 基準リスクレベル | – | – | – |
| 10 ppm | 0.001% | 10 | 約14倍の濃度 | 約14 L | 0.01 | 0.001 |
| 100 ppm | 0.01% | 100 | 約143倍の濃度 | 約143 L | 0.1 | 0.01 |
| 500 ppm | 0.05% | 500 | 約714倍の濃度 | 約714 L | 0.5 | 0.05 |
| 1000 ppm | 0.1% | 1000 | 約1,429倍の濃度 | 約1,429 L | 1 | 0.1 |
| 1450 ppm | 0.145% | 1450 | 約2,071倍の濃度 | 約2,071 L(2トン) | 1.45 | 0.145 |
これらの数値からわかるように、フッ素濃度が高まるほど誤飲や粘膜吸収によるリスクも増加します。
実際に市販されているフッ素配合の赤ちゃんや子供向け歯磨き粉には、配合したフッ素の配合量(ppm値)を明記せずに販売している製品もあり、女性や乳幼児ははっきりしない量の市販製品による安全基準値以上のフッ素暴露リスクに直面している現状があります。
そして大人用の高濃度フッ素1,500ppm配合製品には100gあたり150mgのフッ素が配合されており、赤ちゃんがお腹の中にいるママ、未来のママや赤ちゃんはより多くのフッ素を過剰摂取するリスクが危惧されます。
また口から入る毒を「経口毒」、口腔粘膜を含む皮膚から吸収される毒を「経皮毒」と言いますが、口腔粘膜による「経皮毒」の吸収率は、腕の皮膚が1とすれば、口の中の粘膜は10~20倍とされ、実際には想像以上のフッ素が口残りし、口腔粘膜から赤ちゃんや乳幼児、子供や妊婦の母体、胎児に暴露されていることになります。
家族にあり得る歯磨き粉の使いすぎや誤飲などによる過剰フッ素暴露
家族の安心のために最新の安全情報データから紐解いて、上記の表の様に、
妊娠や授乳中の愛する人が、
1450ppmの高濃度フッ素配合歯磨き粉を、
通常使用量の1グラム(1〜2cm程度)使用して誤飲や粘膜吸収をした場合、フッ素摂取量は1.45mgに相当します。
使用した1グラム歯磨き粉のうち10%(0.1グラム)の口残りで、フッ素0.145mgに相当します。
最新の判決では、妊娠中の母親の尿に含まれるフッ化物0.28 mg/L(0.28ppm、超微量の**0.000028%**に相当)ごとに、子供のIQが1ポイント低下することが予測されると結論付けられています。
歯磨きの回数や粘膜吸収、誤飲や口残りにより、大切な赤ちゃんへのリスク指摘摂取量に近づく可能性があります。
・・・
また大事な自分の赤ちゃんや愛しい子や孫が、
1,000ppmの子供用フッ素配合歯磨き粉を、
推奨の米粒大(0.1 g)や豆粒大(0.25 g)より少し多めの、1グラムを歯ブラシに出し使用して全部を誤飲や粘膜吸収をした場合、フッ素摂取量は1mgに相当します。
使用した1グラム歯磨き粉のうち50%(0.5グラム)の口残りで、フッ素0.5mgに相当します。
最新の判決ではフッ素化物0.7 mg/L (0.7ppm)水道水でも、粉ミルクで育った乳児の IQ に影響が出る可能性があると指摘しています。つまり乳児が飲む1日の水を1リットルとすると、フッ素化物を0.7mg /日を摂取することでのIQ低下リスク報告となります。
こちらも歯磨きの回数や毎日の歯ブラシにつける歯磨き粉の量、飲み込みがちな子供たちは、リスク指摘摂取量に近づく可能性があります。
乳幼児はフッ素を排泄できず、経口摂取した80~90%を長期間にわたって体内蓄積してしまうので注意
特に排泄機能が未成熟な子供がフッ素配合歯磨き粉を日常的に使用すると、吐き出しても一定量のフッ素が体内や脳内に蓄積され、長期間にわたって影響を受ける可能性が高まります。
乳幼児と大人では、フッ素の摂取後の排泄能力が大きく異なります。この違いは主に腎臓の機能成熟度に起因します。新生児や乳幼児は、腎臓の機能が未成熟なため、フッ素や添加物など化学物質を効率的に排泄する能力が低くなります。
大人と乳幼児のフッ素化物摂取による排泄と蓄積の比較
| 項目 | 大人 | 乳幼児 |
|---|---|---|
| フッ素吸収率 | 50~60% | 80~90% |
| 尿中排泄割合 | 50~60% | 10~20% |
| 体内蓄積割合 | 40~50% | 80~90% |
| 排出までの期間 | 24~48時間 | より長期間 |
| 骨への取り込み | 比較的少ない | 多く取り込まれる |
乳幼児では摂取したフッ素の約10~20%しか尿中に排泄されません。残りの80~90%は体内に保持され、骨の形成過程などに取り込まれます。腎臓の機能が成熟するにつれ、徐々にフッ素の排泄能力が向上しますが、完全に成熟するのは2~3歳以降です。
一方大人の場合は、腎臓が十分に発達しているため、摂取したフッ素の約50~60%が尿中に排泄されます。乳幼児では摂取したフッ素の80~90%が体内に保持されるのに対し、大人では40~50%程度です。リスクの差は、乳幼児は排泄効率が低いため、摂取すると体内や脳内の松果体などにフッ素が蓄積しやすく、影響を及ぼすリスクが高まります。
フッ素化物の排泄プロセスと乳幼児への蓄積リスク
フッ素は摂取後、胃や小腸で吸収され、血流を通じて骨などに取り込まれます。一部は唾液や汗で排泄されますが、大半は腎臓を通じて尿中に排出されます。健康な大人では摂取したフッ素の約50~60%が数時間以内に尿中に排出され、24~48時間で多くは体外に排出されます。
一方、乳幼児は腎機能が未熟で、摂取したフッ素の約80~90%が長期間にわたって体内や脳内に残り、骨や松果体などに蓄積されやすい状態にあります。このため、神経発達への影響が懸念されています。特に体重当たりの摂取量が多くなりがちな乳幼児は、大人よりも健康リスクが高いと考えられます。
このように、毎日の少量の誤飲や粘膜吸収でも蓄積による健康リスクが考えられるため、特に子供や妊娠中、授乳中のフッ素配合製品の使用については、各個人の十分なメリットとリスクの考察と自己選択が必要です。
そのうえで妊娠中や新生児の乳歯にも虫歯予防にフッ素塗布が必要と思う方は、歯科医院での歯科医師や歯科衛生士による処置が細心の注意と唾液吸引と共に行い、フッ素の誤飲や粘膜吸収の心配が少ない方法と考えられ、お近くの歯科医院に通院されることが推奨されます。
フッ素化物の脳の松果体への蓄積と不眠やアルツハイマーのリスク
フッ素(特に虫歯予防のフッ素化物)が脳の松果体(pineal gland)に及ぼす影響については、さまざまな研究が行われています。
松果体(pineal gland)は、脳の中心に位置する重要な内分泌器官で、光を感じ、体内時計を調整するホルモン「メラトニン」を分泌し、睡眠と覚醒のリズムを管理します。近年、神経科学の分野では、松果体が集中力、創造性、直感力、さらには知能や判断力の向上に寄与する可能性が注目されています。
西洋医学や神経科学では、松果体の健康が体全体のリズムや精神的な安定性に重要であるとされています。近代西洋医学前の人類医学の歴史では、松果体は「第三の目」と呼ばれるエネルギーセンター(第6チャクラ)と関連づけられ、洞察力や心身の調和を司ると考えられてきました。
第六感とは、一般的に人間の五感(視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚)に加えて、通常の感覚では説明できない「直感的な感覚や知覚能力」を指します。
この小さな器官は、人間の知的・精神的能力を支える基盤として、最新科学と伝統医学の両側面からその重要性が評価されています。
1997年にイギリスの研究では、フッ化物が松果体に蓄積しやすいことが示されました。この研究では、松果体がフッ素を吸収しやすく、結果として松果体の石灰化(カルシウムやリン酸塩の結晶が沈着し、組織が硬くなる現象)が進む可能性が指摘されています。
松果体の機能低下によるメラトニン分泌の減少は、不眠や概日リズム障害を引き起こす可能性があります。一部の研究者は、松果体の石灰化が神経変性疾患(アルツハイマー病やパーキンソン病など)や老化や、免疫力の低下に関連する可能性を指摘しています。
フッ素と松果体の関係に関する研究は進行中であり、特に人間への長期的な影響についてさらなるデータが必要です。飲料水や歯磨き粉からのフッ素摂取量を適切に調整し、潜在的なリスクを最小化することが求められています。
脳内メラトニン分泌による良い睡眠とリカバリーを求める方は、一定時期フッ素摂取を行わない場合の、睡眠や集中力、判断力や体調の変化などの様子を見てみることも各個人にとってできる実験といえ、試しに一度行ってみる価値はあると考えます。
以上のことを鑑みると、成長中の小さな赤ちゃんの、神経が脳まで直接通った柔らかい乳歯に、超高濃度フッ素を投与することは、発達中のごく小さな脳や松果体にリスクが生じることはないのか、我が子のためには安全性の確認が必要と考えられます。
赤ちゃんや乳幼児が、初めてフッ素を口に入れる時に驚くほど大泣きして嫌がる事や吐くこと、毎日のフッ素での歯磨きを嫌がるというのは、幼いなりにも賢い人間の本能が持つ直感的な感覚から、フッ素の味がどうしても受け入れられないものなのか、理由は口では説明できないが神経毒から自らの脳を守る、できる限りの抵抗であったかと見れるか反応観察が必要です。
フッ素は男の脳にも影響する、筋トレ中や妊活中の愛する人にも注意
またフッ素暴露により男性の内分泌機関や生殖機能へのリスクも指摘されています。テストステロン等の男性ホルモン低下による、やる気減退、生産性低下、筋肉減少、体力低下、鬱、更年期障害また性欲や生殖機能の低下により、少子化につながる可能性が以下の研究で指摘されています。
2003年にメキシコでフッ素(3.0 ppm)を含む飲料水に曝露している 160 人の男性について、フッ素摂取と性ホルモンレベルに関する疫学研究を実施。高曝露群では低曝露群に比較して血清中の卵胞刺激ホルモン(FSH)が有意に高く(p<0.005)、インヒビン B、遊離テストステロン、プロラクチン32は有意に低かった(p<0.005)。3~27 mg F/日でのフッ素曝露は生殖系の細胞に影響を与えるとしている(Ortiz-Perez et al. 2003)。
特にテストステロンの低下は、筋トレに励んでいる方や体力の維持を心がけている方、最近元気のない方や男性ホルモンの低下する年齢の方、テストステロン療法を行っている方や妊活中の方、仕事やスポーツを充実させたい方にとっては、避けるべきであるとされています。
子供の脳の発達にパパやママが注意すべき時は
人間の人生の中で、脳に影響を与える可能性が高い時期は、胎児期から乳幼児期だとされています。この結論は、近年の研究やレビューから以下の点で支持されています。
1. 胎児期(妊娠中)
背景: 胎児の脳は妊娠中期(第2トリメスター)から急速に発達し、この時期に外部からの影響を受けやすい。
研究結果:
カナダの研究(2019年)では、妊婦の尿中フッ素濃度が高い場合、その子どものIQが低下する傾向が示されています。
特に男児のIQに影響が大きいとの結果が多い。
胎盤を通じて母親の体内のフッ素が胎児の発達中の脳に影響を及ぼすと考えられています。
2. 乳幼児期(0~2歳頃)
背景: この時期は脳の発達が著しく、神経系の形成が進む時期であり、外部の化学物質への感受性が高い。
リスク要因:
粉ミルクをフッ素濃度の高い水で調整した場合、乳幼児が過剰なフッ素に曝露される可能性があります。
松果体(脳の内分泌器官)が発達中であり、フッ素の沈着による機能低下が指摘されています。
影響: 幼児期の過剰なフッ素摂取が、認知能力やIQに長期的な影響を与える可能性があるとする研究があります。
3. 幼児期(3~7歳)
背景:引き続き脳の発達が続き、IQに環境や学習が影響を与える時期です。脳の保護と教育が重要です。
リスク要因:
高濃度フッ素の場合、適量以上を誤飲、蓄積リスクで過剰暴露の可能性が高い。
4. 学童期(8歳以上)
背景:学力や社会性が求められ、成績やコミュニケーション力、受験や勉強に脳の発達が影響する。
この時期あたりから学校のテストなどで子供の学力や知能差が分かり始める。
リスク要因:
高濃度フッ素の場合、適量以上を誤飲、蓄積リスクで過剰暴露の可能性が高い。
なぜ以上の時期が最も危険か
・脳の発達期: 脳の神経回路やシナプス形成が最も活発に行われる時期であり、この過程がフッ素などの外部要因に敏感。
・排泄能力の未発達: 乳幼児は腎臓機能が未熟であり、フッ素を体外に排出する能力が低いため、体内に蓄積しやすい。
この時期に母親や乳幼児が過剰なフッ素に曝露されないようにすることが、子どもの健康な脳発達のために特に重要です。研究の多くはフッ素の影響を防ぐために、妊娠中や授乳中、乳幼児期のフッ素摂取を適切に管理することを推奨しています。
子供は6歳〜12歳の間に乳歯から永久歯に生え変わります。たとえ赤ちゃんの頃からの乳歯が虫歯になっても、体の他の排泄機能等の成長に伴って6歳以降には、その後に丈夫な永久歯が生えてきます。フッ素化物による歯牙の強化が依然必要と思う親は、子供の腎臓と排泄機能が発達した6歳以降の永久歯からの方が、総じてリスクを下げられると考えられます。
高い知能と豊かな人生への影響について
メディアが伝える様に脳へのダメージによる発達障害、ADHDや不注意のリスクの増加などを含む子供の知能指数(IQ)の低下は人生に深刻な被害をもたらし、研究ではIQが1~2ポイント低下するだけで、例えば教育達成度(知能・学力・成績・偏差値・進路)、雇用状況(就職・転職)、生産性(能力・集中力・観察力・理解力・判断力・想像力・行動力等)、賃金の低下(所得格差・貧困格差)につながることが分かっています。
また子供だけでなく大人にとっても高齢層の認知機能の低下(物忘れ・アルツハイマー・呆け・介護)、勤労世代の生産性(仕事・能力・判断力・成績・昇進・元気・賃金)の低下など様々なリスクが米国においては指摘されています。
高い知力を有することは現代社会において、体力と同様に人生を豊かにするといわれ、世界中の親たちは子供たちの将来の幸せを願っています。
自分の情報や知識レベルに合わせた判断で我が子を守る
ただ過剰暴露リスクが指摘される高濃度フッ素配合製品について、今回の判決の全アメリカ国民が使用する水道水への強制フッ素添加、集団フッ素暴露と異なり、高濃度フッ素歯磨き粉は約1ドルという安価でどこでも買える現状では、自己選択で消費者はフッ素を使用・購入しないで回避する個人の自由があり、FDA(アメリカ食品医薬品局)による一般市場に流通している高濃度フッ素配合歯磨き粉や洗口液等への流通規制は、先になるであろうと予測されています。(すでにフッ素配合歯磨き製品への危険毒性表記規制あり)
よって、妊娠中や赤ちゃん子供のいる消費者で、子供の成長発達に興味のある方は、我が子の健康と未来を自分自身の情報収集と自己選択、自己防衛で守っていくことが必要とされています。
フッ素の水道水への添加による集団暴露については、人権的な側面として情報弱者や所得の低い人々には回避できない不当なリスクと判決されていますが、市販のフッ素配合製品の消費者の自己選択は個人の自由となり、個人・能力主義のアメリカ社会においては、それぞれの親の情報収集力や自己判断力など親世代の知能や能力の違いにより、子供世代の能力や所得格差をさらに広げ格差社会を助長する要因や、格差の自己責任論の深化にもなりうると指摘されています。
IQ・知能指数は50〜80%が親からの遺伝要素といわれ、成人後は親からの遺伝影響が80%になるといわれていますが、5歳程までの幼少期は環境や教育により遺伝的な限界を超えてIQ・知能指数を高める可能性を持っています。よって胎児や幼少期は脳の保護と健康に加え、環境や教育が重要とされます。
幼少期の環境や教育の質は、成人後のIQ・知能指数だけでなく、学業成績、職業選択、社会的スキルにも影響を与えます。脳が守られ、教育が豊かな環境で育った子供は、自己制御能力や創造性、問題解決能力においても優れた能力を発揮する傾向があります。
いつ頃から高濃度フッ素暴露の脳への危険性が指摘され始めたのか
高濃度フッ素暴露が脳に与える影響についての懸念は、1990年代頃から本格的に研究され始めました。以下のような研究が、フッ素と神経発達に対する懸念を高めるきっかけとなりました:
- 1990年代から2000年代初頭 – 一部の研究により、フッ素が高濃度で曝露された場合、神経毒性がある可能性が指摘されました。この時期の研究は主に動物実験や発展途上国での事例をもとに行われ、脳や神経発達へのリスクについてのデータが収集されました。
- 2000年代後半から2010年代 – カナダや中国、メキシコの研究において、妊娠中の母親が高濃度のフッ素に曝露されると、子供のIQ低下のリスクが高まる可能性があることが報告されました。この頃から、特に子供の神経発達に影響する可能性が注目され始め、研究の質も高まりました。
- 2010年代後半から2020年代初頭 – 神経毒性とフッ素の関連を示すエビデンスが蓄積され、IQや神経発達リスクに対する懸念が科学界でさらに強まりました。2019年のカナダの研究や、米国環境保護庁(EPA)や国立毒性プログラム(NTP)による評価もこの懸念を支持し、神経発達リスクを確認する報告が出されました。
- 2024年の米国判決 – 9月24日に、米国連邦裁判所がフッ素のリスクに関する規制強化を命じる判決を下し、フッ素が子供の知能指数(IQ)に与えるリスクについての懸念が法律的にも大きく取り上げられました。この判決により、水道水におけるフッ素濃度の再評価と規制強化の義務が生じ、今後も研究が続くと考えられます。
このように、フッ素の脳や神経への影響についての懸念は長期にわたって存在し、特にこの20~30年で科学的エビデンスが増え、懸念が強まりました。
なぜヨーロッパ人の方がフッ素を避ける傾向にあるのか フッ素の発明はフランスから
フッ素の発明(単離成功)はヨーロッパのフランス発といえ、フッ素の研究は1886年に単離に成功し1906年にノーベル化学賞を受賞したフランス人科学者アンリ・モアッサンが有名です。その新しいエネルギー技術で、現在も産業的地位を維持しています。
ヨーロッパでは古くから製鉄などにおいて、フッ素の原料である蛍石(フロライト)を融剤として用いられてきました。ドイツの鉱物学者ゲオルク・アグリコラは1530年に著書『ベルマヌス(Bermannus, sive de re metallica dialogus)』において、蛍石(フロライト)を炎の中で加熱し、融解させると、融剤として適切であると記しています。
1670年には、ドイツのガラス加工業者のハインリッヒ・シュヴァンハルトが蛍石(フロライト)の酸溶解物にガラスをエッチングする作用があることを発見しました。蛍石(フロライト)に硫酸を加えると発生する「フッ化水素」は1771年、スェーデンの科学者カール・シェーレが発見しました。フランスのアンドレ=マリ・アンペールは、未知の元素が蛍石(Fluorite)に含まれる可能性から、未発見の新元素に「fluorine」と名付けました。
しかし当時は世界の叡智を持ってしても、フッ素は単離できませんでした。最終的に1886年にフランスの科学者アンリ・モアッサンが単離に成功しました。白金・イリジウム電極を用いたこと、蛍石をフッ素の捕集容器に使ったこと、電気分解を**−50°Cという低温下**で進めたことが成功の鍵でした。そして、1906年にノーベル化学賞を受賞します。出典:Wikipedia
その後20世紀、1900年代のヨーロッパは、フッ化水素とフッ素化合物の発明や応用において先駆的な役割を果たしました。エネルギー、冷媒、テフロン、農薬、医薬品など、多くのフッ素関連製品が開発され世界をリードしました。
しかし21世紀に入り2000年代以降、資源枯渇や製造人件費コストの国際競争により、蛍石(フロライト)やフッ素関連製品の生産は次第に他の地域(特にアジア、中国、インドなど)に移行、ヨーロッパでは環境規制を進める政策を取りました。
今日では、フッ化水素とフッ素化合物の生産の中心は中国をはじめとするアジア諸国です。これらの国は、フッ化水素とフッ素化合物の原料である蛍石(フロライト)の豊富な埋蔵量や低コストの生産環境を背景に、世界の主要なフッ素原料と関連製品の生産国となっています。
一方で、ヨーロッパはフッ素関連製品の主要な消費国としての地位を維持しています。特に自動車、航空、医療などの産業における高機能フッ素材料の需要が高いです。ドイツとフランスのエネルギー政策は大きく異なりますが、EU全体としては現在はPFASの環境規制に力を入れています。
フッ素研究の先進国として進んだ、ヨーロッパ人のフッ素の健康リスクへの懸念
21世紀となった今のヨーロッパで、水道へのフッ素添加が広く受け入れられていない理由は、歴史的背景、健康リスクへの懸念、そして異なる公衆衛生政策に基づいています。以下がその主な要因です:
- 歴史的背景と慎重な政策
フッ素研究の先進国としてヨーロッパでは、フッ素添加水の普及が進んだ時期でも、アメリカほど積極的に導入されませんでした。フッ素の虫歯予防への効果や安全性について慎重な意見が多く、一部の研究者や政府がリスクを指摘していたため、政策として採用する国が少なかったといえます。結果として、水道水のフッ素添加はヨーロッパでは例外的な措置とされ、フッ素を直接水道水に添加しなくても虫歯予防が可能という考えが広まりました。 - フッ素の健康リスクへの懸念
フッ素が神経や骨に与える影響についての科学的研究が蓄積するにつれ、ヨーロッパではフッ素を避けるべきとする意見が強まっていきました。特に近年の研究で、フッ素の神経毒性や知能低下リスクが報告されると、一部の地域でフッ素添加を再評価したり、完全に禁止する動きが増えました。 - 欧州連合(EU)の厳しい規制
EUでは、環境や健康に関する規制が厳格であるため、フッ素についてもリスクが疑われる段階から抑制する姿勢が取られました。EUの規制に従うことで、加盟国の多くがフッ素添加水を提供せず、虫歯予防は他の方法で実現する方針が一般的です。 - 代替手段の普及と教育
ヨーロッパでは、フッ素に依存しない虫歯予防策として、歯科医による定期的なケアや食生活改善、歯磨きの普及が徹底されています。また、フッ素の代替として効果がある他の成分や技術が研究・導入され、特にフッ素フリーの歯磨き粉も一般的です。 - 消費者の健康意識
ヨーロッパの消費者は、天然素材やオーガニック製品への志向が強く、フッ素のような添加物に対しても敏感です。健康へのリスクが少しでも示唆される成分には注意を払い、選択肢があれば、より安全で自然な製品を好む傾向があります。
約40年前の1980年代後半から1990年代前半、フッ素の脳への影響に関する研究が本格化する以前、北ヨーロッパのスウェーデンにあるイエテボリ大学の研究者は、歯磨き後にフッ素を歯に長く留めることで虫歯予防効果を高める「イエテボリ法(Gothenburg Technique)」を提唱しました。この方法では、フッ素濃度1,000~1,450ppmの歯磨き粉を使用し、歯磨き後は軽く吐き出して水ですすがないことが推奨されました。
ただし、フッ素の適切な使用が求められるため、イエテボリ法は12歳未満の子供には推奨していません。さらに、スウェーデンでは現在に至るまで水道水のフッ素化は行われていない状況です。
これらの要因により、ヨーロッパではアメリカやその他の国々と異なり、水道水へのフッ素添加があまり推奨されておらず、消費者の間でもフッ素摂取を避ける傾向が続いています。そして政策面ではフロンガスやPFAS規制の推進等、フッ素関連物質への環境規制を推進しています。
虫歯予防のフッ素の原料は
日本では、虫歯予防に使用されるフッ素(Fluorine, F)の原料である蛍石(ほたるいし/けいせき、フルオライト)は、主に中国から輸入しています。アシッドグレード蛍石(CaF₂含有率97%以上のフルオライト)は、主にフッ化水素の製造に使用される高純度の蛍石(フロライト)で、歯磨き粉や洗口液への添加など、虫歯予防に広く利用されています。
過去30年間にわたり、日本のアシッドグレード蛍石(フロライト)の主輸入元は中国です。1990年代: 日本への輸入量の約50%を占め、最大の供給国に、2000年代以降: 生産量の増加に伴い、輸入割合は約67%に達する、現在、日本のアシッドグレード蛍石(フロライト)の供給量の約60-70%のシェアを維持しています。
輸入量の推移は、1990年代: 日本全体のアシッドグレード蛍石(フロライト)輸入量は約20万トン、2000年代: 輸入量が30万トンを超える、2010年代後半: 約35万トンに達しています。出典:JOGMEC資料: 日本鉱物資源機構 (JOGMEC) – 輸入量と供給国の詳細。
虫歯予防のフッ化物の製造方法は
虫歯予防に広く使用される無機フッ化物は、工業的な方法で生産されます。その原料となるのは、自然界に存在する蛍石(ほたるいし/けいせき、フルオライト)です。フッ化カルシウム(CaF₂)を含むこの鉱物は鉱山から採掘され、粉砕された後に化学反応に利用されます。
フッ素が自然界にある元素であるからといって、濃度が薄く安全な海水や植物、生物など地上の自然界から採集する確立した技術はありません。虫歯予防のフッ化ナトリウムなどは、地底から採掘した鉱物の蛍石(フロライト)を基に化学反応で生産される化学物質なのです。
まず、フッ化カルシウムを硫酸(H₂SO₄)と化学反応させることで、フッ化水素酸(HF)が生成されます。この化学反応では副産物として硫酸カルシウム(CaSO₄)が生じます。生成されたフッ化水素酸は、無機フッ化物を作るための重要な中間体となります。
次に、フッ化水素酸を中和反応などで処理し、用途に応じた無機フッ化物を製造します。たとえば、フッ化ナトリウム(NaF)はフッ化水素酸と水酸化ナトリウム(NaOH)を化学反応させることで作られます。一方、フッ化スズ(SnF₂)はフッ化水素酸と酸化スズ(SnO₂)の化学反応によって得られます。
生成された無機フッ化物は、最終的に純度を高めるために精製されます。その後、粉末や液体など用途に応じた形態に加工され、歯磨き粉や水道水のフッ化処理に使用されます。
蛍石(フロライト)からつくられる産業上重要なもの
蛍石(フロライト)は、産業界で幅広く利用される重要な鉱物で、新しいエネルギー産業に重要なフッ化水素酸(HF)の原料として知られています。
フッ化水素酸は、アルミニウム製造や冷媒(フロン、HFC、HFO)の生産、フッ素樹脂(例:PFAS)などのフッ素化学製品の基盤となります。また、ガラス加工や金属精錬のプロセスでも欠かせない役割を果たしています。さらに、高純度の蛍石は特殊ガラスや光学機器(例:カメラレンズ、望遠鏡)の製造にも利用され、色収差を抑える特性が求められる分野で利用されています。
鉄鋼業やアルミニウム精錬では、蛍石(フロライト)がフラックス材として使用され、不純物の除去やスラグ形成を助ける重要な役割を果たします。さらに、蛍石(フロライト)を基にフッ化水素酸と共に生産されるフッ素化学製品は、歯磨き粉や水処理、リチウム電池の電解質、半導体製造など、日常生活や先端技術の分野で欠かせません。
そのため、蛍石(フロライト)の供給不足や価格変動が産業全体に与える影響は大きく、環境規制や輸出制限が課題となっています。
蛍石(フロライト)の採掘と健康、日本での歴史
蛍石(フロライト)は美しい石で、主にエネルギー生産に用いられるフッ化水素酸 、その他フッ素化合物の原料、工業用溶剤として使用される鉱物です。
世界では、以下の地域がその主な産地として知られています。
・中国: 世界最大の蛍石(フロライト)生産国で河北省、内モンゴル自治区、浙江省、四川省、湖南省などが主要採掘地域で、地球上の蛍石(フルオライト)埋蔵量の約60%を占めています。
・メキシコ: ハリスコ州やコアウイラ州の鉱山が多く、特にアメリカ向けの輸出が盛んです。
・南アフリカ: リンポポ州などが主要地域で、品質の高い蛍石(フルオライト)を輸出しています。
・モンゴル: 中国市場向けの供給源として重要な役割を果たしています。
・スペイン: カスティーリャ・イ・レオン地域がヨーロッパの重要な産地です。
かつて日本でも蛍石(フロライト)の採掘が行われていました。特に以下の地域が採掘地として知られていました。
福島県: 安達太良山周辺。
岐阜県: 複数の鉱山が存在していましたが、現在は閉山。
北海道: 一部地域で採掘されていました。
しかし、日本の蛍石(フロライト)採掘は鉱山の枯渇と国際競争力から1960年代以降に縮小し、多くの鉱山が閉山。現在では国内での採掘は行われておらず、中国から輸入しています。
各国別の蛍石(フロライト)生産量の推移予測(単位:千トン)
| 年度 | 中国 | アメリカ | ロシア | インド | ブラジル | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 10 | 100 | 50 | 5 | 10 | 200 |
| 1950 | 50 | 300 | 150 | 20 | 30 | 400 |
| 2000 | 300 | 150 | 100 | 100 | 60 | 200 |
| 2025 | 1000 | 100 | 60 | 150 | 100 | 90 |
中国ではフッ素は毒 1億人以上がフッ素過剰暴露と中毒の社会問題
中国では、1980年代に広東省の一部地域で水道水へのフッ化物添加が試みられました。具体的には、広州市の芳村地区で18年間、莞城鎮で11年間にわたり実施されました。芳村地区では、フッ化物添加により永久歯のDMFT(虫歯の数)や乳歯のdftが著しく減少する効果が確認されましたが、一時的にフッ化物の過剰添加により歯牙フッ素症の問題が発生しました。一方、莞城鎮では0.6ppmの適切な濃度でフッ化物添加が行われ、歯牙フッ素症の問題は発生しませんでした。J-STAGE
フッ素の原料である蛍石(フロライト)の地球上60%の埋蔵国であり、水道水にフッ素を添加する以前に井戸水に高濃度で含まれており、環境中のフッ素による住民のフッ素中毒患者が多く、逆に如何に飲み水や食品、大気中からのフッ素暴露によるフッ素中毒を減らすかという課題があります。
2003年の日中の共同研究では、フッ素汚染地域は、飲料水としての地下水がフッ素に汚染されている地域と、フッ素含量の高い石炭や土壌を使用し、燃焼に伴う屋内フッ素汚染による暴露が起こっている地域に分けられ、これらの地域においてはフッ素汚染により、慢性のフッ素中毒である歯の形成異常(歯牙フッ素:斑状歯)と骨フッ素症(骨硬化症)が発生してるとしています。
人口13 億人の中国で、全国 32 の省、自治区、直轄市のうち、上海市を除く 31 省、自治区、直轄市において、つまりほぼ中国の全域で特定地域の住民がフッ素汚染に曝されています。その結果、日本の人口と同じくらいの約1億人の人がフッ素汚染上リスクのある地域に居住し、歯牙フッ素症患者の総数は、約 4,300 万人に上ると報告されています。
また中国は、国内に埋蔵される豊富な石炭に依存した急激な経済発展を成し遂げつつあり、このうち石炭燃焼に由来するフッ化物による「屋内汚染(屋内での石炭使用による石炭に含まれる蛍石・フッ素による吸引暴露)」は 14 の省において報告されており、フッ素の直接吸入と食品汚染を介した間接暴露によって、フッ素症が起こっています。
四川省や貴州省などの一部では、フッ素含量が 500mg/kg(500ppm) を超える調整炭を暖房や調理のため石炭ストーブで使用している地域もあり、燃焼によって高濃度のフッ素が発生し、家屋内汚染が深刻化しています。1997 年の中国衛生部の報告によると、石炭燃焼由来のフッ素症の患者は、斑状歯が 1,817万人、骨フッ素症が 146 万人に及んでいます。
以上の理由から中国では「フッ素は毒物である」とされ、人の健康にとってはフッ素は身近に無い方が良いもので、フッ素汚染地域の1億人以上の国民をどのように守るか、フッ素が元々含まれる地下水からどのようにしてフッ素を除去するのかが重要なことであり、歯磨き粉に含まれるフッ素の毒(急性・慢性中毒や神経毒性)についても歴史を通して周知しているものと思われます。
フッ素中毒による斑状歯や骨フッ素症は、治すことはできず予防するしかなく、蛍石(フロライト)の産地でありフッ素汚染の多い中国では、多くの人々を大気中や飲み水、食品、屋内での石炭使用によるフッ素暴露と中毒から守るため、フッ素の人体への健康被害や環境への悪影響について、現在では様々なフッ素化物への国内規制を講じ人々のフッ素中毒は減少していると考えられます。
規制が進む有機フッ素化合物(PFAS)と無機フッ素化化合物(フッ素、フッ素化物、フッ化物)の違いは?
フッ素(Fluorine, F)は世界で話題になっていますが、いま日本で話題のフッ素は2種あるので区別が必要と唱える人もいます。
鉱物(ハロゲン化鉱物)の蛍石(フロライト)からつくり出されるフッ素(Fluorine, F)とは、周期表の17族(ハロゲン)に属する元素で、原子番号9、化学記号Fの非金属元素です。自然界で最も電気陰性度が高い元素であり、他の物質から電子を奪う能力が非常に強力です。この特性により、フッ素は非常に反応性の高い酸化剤として知られています。
単体のフッ素(F₂)は、常温で淡黄色の有毒な気体として存在し、多くの物質と激しく反応します。自然界では単体としては存在せず、主に無機フッ素化合物(フッ素イオンを含む化合物)として蛍石(フロライト)に含まれています。
フッ素は、エネルギーに欠かせないフッ化水素酸の他、歯のエナメル質の強化や虫歯予防に利用される無機フッ素化合物(例:フッ化ナトリウム)、有機フッ素化合物(例:PFAS)として、冷媒、半導体材料、耐熱ポリマーなどを含む産業用途にも広く使用されています。
化合物とは、2種類以上の異なる元素が化学結合によって結びついてできた物質で、
有機化合物とは、「炭素(Carbon)を主成分」とし、炭素-炭素結合や炭素-水素結合を含むもの、
無機化合物とは「炭素(Carbon)を主成分としない」もの、または特定の炭素化合物です。
有機フッ素化合物(PFAS)とは フッ素がしみこんだ炭 水に溶けず永遠に環境に残る
有機フッ素化合物(PFAS)は、「フッ素(Fluorine, F)が、炭素(Carbon)と結びついた化合物」で、現在危険視されているPFOSやPFOA等の1万種類以上の化学物質の総称、水や油をはじく効果があり、熱にも強いことから、フッ素樹脂加工のフライパンや半導体、冷媒、包装紙、防水服、消火器などに幅広く使われてきました。簡単に言えば気体のフッ素がしみこんだ炭です。
有機フッ素化合物(PFAS)は、高い耐久性を持ち「永遠の化学物質(フォーエバーケミカル)」として知られ、環境中や体内への蓄積および健康への影響が懸念されています。欧米では、1980年代までは主要生産国でしたが、1990年代からその有害性が注目されました。アメリカでは2000年にPFOSを製造していた企業が自主的に生産を中止し、EPAによる規制が強化されました。欧州連合(EU)は2006年にPFOS規制を開始し、2010年以降にPFOAを含む他のPFASを追加で規制しました。日本では全国の水道水や水源汚染が問題となっています。
有機フッ素化合物(PFAS)はアメリカで、「乳児・胎児の発育の低下」、「脂質異常症(悪玉コレステロールや中性脂肪の増加)」や「腎臓がん」などの副作用、日本の食品安全委員会では、「流産・早産」や「免疫機能の低下」、「がん」などのリスクが指摘されています。
無機フッ素化合物(フッ素、フッ素化物、フッ化物)とは フッ素がしみこんだ塩 水に溶けて永遠に環境に残る
一方、虫歯予防に用いられる無機フッ素化合物(フッ素、フッ素化物、フッ化物)は、「フッ素(Fluorine, F)が、炭素(Carbon)以外の元素(例: ナトリウム・Na、カルシウム・Ca)と結びついた化合物」で、フッ化ナトリウム(NaF)やフッ化スズ(SnF₂)などの化学物質です。アルミニウムやウランの製造過程などにも生じる高い腐食性を持つ物質で、アメリカで1950年から約70年間に渡り、虫歯予防として水道水や歯磨き粉に添加を行ってきた物質です。簡単に言えば気体のフッ素がしみこんだ塩などです。
日本の歯磨き粉で使用される無機フッ素化物(フッ素、フッ素化物、フッ化物)の表示名称は以下のようなものがあります。
・「フッ化ナトリウム(Sodium Fluoride, NaF)」:主に虫歯予防の効果を持つフッ素化合物で、多くの歯磨き粉に使用されています。
・「モノフルオロリン酸ナトリウム(Sodium Monofluorophosphate, MFP)」:同じく虫歯予防効果を持つフッ素化合物ですが、ややマイルドな特性を持っています。
・「フッ化第一スズ(Stannous Fluoride, SnF₂)」:歯の再石灰化を促進し、歯茎の健康維持にも役立つと言われていますが、日本ではあまり一般的ではありません。
無機フッ素化合物(フッ素、フッ素化物、フッ化物)は2024年9月のアメリカの最新判決で、全米3億3,000万人が利用する水道水において、急性・慢性中毒量以下の現状のフッ素添加0.7ppm水道水での子供の知能低下リスクが判決され、全米でニュースになっています。
また、虫歯予防のフッ素化物は、海の水に溶けている自然界のフッ素や植物中から採取できる確立された技術はありません。フッ素化物を含む蛍石(フロライト)からフッ化水素を作り、フッ素化ナトリウム等はその利用時に産出され生産されるものです。
つまり、有機フッ素化合物と無機フッ素化物は、まったくの別物などではなく、共に同じ蛍石(フロライト)から生み出されるフッ化物です。
虫歯予防のフッ素化物とPFASはともに永遠の物質 規制による産業への影響は
フッ素とPFAS(パーフロロアルキル化合物)はどちらも“永遠の物質”として注目される特性を持っています。しかし、それぞれの性質や環境への影響、規制の背景には重要な違いがあります。この違いを理解することで、両者の共通点や相違点、そしてそれぞれの規制が産業や社会に与える影響について考察することができます。
フッ素は自然界に広く存在する元素であり、蛍石(フロライト、CaF₂)や地下水などの形で見られます。フッ素化物(F⁻)は水に溶けやすく、自然環境では安定して存在します。この安定性が“永遠の物質”という印象を与える要因の一つです。フッ素化物は蛍石(フロライト)から人工的に採取されたものになります。
一方、PFASは人工的に作られた化学物質で、炭素とフッ素の非常に強い結合を特徴としています。この結合は自然界で分解されにくく、環境中に長期間残留します。そのため、PFASは“永遠の化学物質”と呼ばれ、特に人体や環境への悪影響(発がん性、ホルモン撹乱作用など)が懸念されています。PFASは撥水性や耐熱性を求められる製品(例:フライパンのコーティングや防水布、消火剤)に広く利用されてきましたが、その毒性から規制が進んでいます。
このように、フッ素化物とPFASはどちらも“分解されにくい”という特性を共有していますが、いくつかの点で異なります。フッ素化物は人工的に採取された物質である一方、PFASは人工的に設計された化学物質です。
さらに、「PFAS環境規制は資源規制にあたるのではないか?」という視点も興味深いですが、本質的には異なる問題です。PFAS環境規制の目的は、人工的に作られた耐性化学物質による環境や健康へのリスクを最小化することです。一方で、自然由来のフッ素そのものは、自然界に広く存在するため規制対象にはなりません。
ただし、フッ素化物の使用が長期的に蓄積し環境に及ぼす影響(例:飲料水フッ素化政策など)は、PFASに関する議論と類似点があります。
PFASは半導体製造において重要な役割を果たし、特にフォトリソグラフィ工程で不可欠な化学物質です。その耐熱性や耐薬品性から、他の物質では代替が難しい特殊な機能を提供しています。しかし、PFAS環境規制が厳格化されると、製造工程の再設計や代替物質の開発が求められ、宇宙産業や先端テクノロジー産業全体に大きな影響を及ぼします。
PFAS環境規制が先端産業規制に深い影響を与える一方、フッ素化物健康規制も産業規制に関連性があると考えることもできます。フッ素化物も産業において重要な役割を果たしています。しかしフッ素化物の利用が増えることは環境や健康へのリスクを伴うため、厳格な規制が求められます。フッ素化物健康規制が産業全体の安全性や持続可能性を管理する役割を果たすといえます。
これらのフッ素化物の環境や健康への規制はそれぞれ異なる産業に影響を与えていますが、共通するのは“持続可能性”や“安全性”を重視する点です。これらの議論は、科学技術の進歩と環境保護、そして倫理的な視点が交差する人類にとって重要なテーマです。
外来の高濃度フッ素で環境汚染リスク? PFAS規制と水道水フロリデーション中止は実質フッ素全般規制か
フッ素は無機でも有機でも水に溶けたり溶けない形で、自然界にフッ素は残り続けます。フッ素は地球上から蒸発したり消滅したりはしません。環境中に濃度を変えて濃縮蓄積し続けます。
無機フッ化物は水溶性が高く、環境中で溶解・拡散する傾向があります。水に溶けて残る物質です。有機フッ素化合物は疎水性で難分解性があり、生物体内で蓄積しやすい特性があります。
つまり、有機フッ素化合物と無機フッ素化物は、全くの別物などではなく、同じ蛍石(フロライト)にから生み出されるフッ化物で、環境中に残り続ける物質です。
虫歯予防のフッ素(無機フッ化物)も、環境汚染の原因となる可能性があります。土中や地下水や井戸水に蓄積されたフッ素は、飲料水や作物を汚染してしまいます。
ちなみに、アメリカで規制される有機フッ素化合物PFASの量は 4 ng/L(0.000004 ppm) と非常に微量です。一方、これまでの無機フッ素化物の推奨水道水濃度は 0.7 ppm(700,000 ng/L) です。これを比較すると、無機フッ化物はPFASの規制濃度の約175,000倍に相当します。
フッ素は自然界に広く存在する元素で、通常はフッ化物(化合物の形態)として自然界に見られます。化学的に安定している物質の一方で、高濃度では毒性を持ち、生態系や人間の健康に影響を与えることがあります。フッ素化が適切に管理されない場合、排水や水道水添加によって川、湖、地下水に蓄積する可能性があります。高濃度のフッ化物は水中生物に有害となり、魚類や植物の生存に悪影響を与えます。
また、そうしたフッ素濃度が高い水を長期間飲用すると、慢性のフッ素中毒である歯の形成異常(歯牙フッ素:斑状歯)と骨フッ素症(骨硬化症)につながる可能性があります。フッ化物が土壌に蓄積すると、微生物や植物に悪影響を及ぼし、農業生産性の低下や植物の成長阻害を引き起こします。さらに、産業活動でフッ化物が大気中に放出されると、酸性雨の原因となったり、植物の葉に吸収されて成長や収穫量を減少させたりすることがあります。
工業的なフッ化物の排出は多くの国で厳しく規制されており、例えば排水中のフッ化物濃度には厳しい基準が設けられています。日本でも飲料水のフッ化物濃度は0.8ppm以下に規制されており、フッ化物を含む廃棄物は「特別管理産業廃棄物」として専門施設で処理されています。
高濃度での環境中への排出は生態系や人間の健康に影響を及ぼす可能性があります。特に、水生生物に対する毒性や土壌への蓄積が懸念されます。したがって、フッ素含有製品の使用や廃棄に際しては、適切な管理と環境への配慮が求められます。長期間大量に使用され、地下に濃縮蓄積していく場合、水質汚染や土壌汚染、大気汚染、生態系破壊を引き起こすリスクがあります。
また自分自身が住む周りの環境がフッ素に汚染されておらず美しい環境であるならば、河川から飲料水や水産物を汚染し、農作物や土壌を汚染する外来の高濃度フッ素製品を、あまり下水を通して近隣の美しい川や海に、排出しない方が良いと考えます。もし近隣の飲料水に用いられる地下水が今回の判決で示されたリスク量の0.7ppm以上のフッ素量となった場合は、注意が必要です。
地球上の別の大陸の地底深くに濃縮蓄積されて元々あった外来の高濃度フッ素を、近隣の自然環境に排出し、濃い場合の毒性も最終的に海で薄まって安全という考えですが、このまま続くといつか近所の地下水や水道水、作物や水産物中のフッ素量が増えて高濃度地域と同じようになり、貴重な水や作物が飲めなくなり食べられなくなると考えられます。
もし身近に高濃度フッ素汚染がない恵まれた美しい自然環境があるのなら、その環境中に外部から持ち込まれた化学物質を排出し続け、近隣環境中の汚染に進めることとは、地域の未来の飲料水や大気など生活環境や農作物や魚や貝への影響、美しい土地の持つ資産価値を維持する為に回避すべきと考えられます。
フッ化物のリサイクルや処分方法は?
無機フッ素化物のリサイクルや処分には、環境負荷を抑えながら安全性を確保するための高度な技術が求められています。まず、リサイクル技術としては、湿式再生プロセスがあり、フッ化物を水溶液中で処理することで不純物を分離し、再利用可能な形態に戻すことができます。また、乾式プロセスでは高温処理により純粋なフッ化物を生成する方法が採用されており、これにより半導体やガラス工業で使用される高純度のフッ化物を生産できます。さらに、化学的変換によって使用済みのフッ化物を別の化学物質に変えることで、他の用途で再利用する技術も進められています。
濾過採集技術においては、特に水中や粉塵中に含まれるフッ化物を効率的に捕捉する方法が重要です。逆浸透膜技術は、水中のフッ化物を効果的に除去する方法で、飲料水や産業排水処理において広く使用されています。また、イオン交換樹脂を用いてフッ化物イオンを捕捉するイオン交換法は、工業廃水処理において高い選択性を発揮します。さらに、凝集・沈殿技術では、フッ化物をアルミニウムやカルシウムと反応させて不溶性の沈殿を生成することで除去する手法が採用されています。これに加えて、エレクトロダイヤリシスを利用した電気分解によるフッ化物除去技術も、高度な処理方法として注目されています。
使用済みフッ素化物の廃棄や処分においては、安全な処理が求められます。安定化と固化の方法では、フッ化物をセメントなどと混合して埋立地で安全に処分することが可能です。また、化学処理では酸や塩基と反応させてフッ化物を無害化する技術が用いられており、例えばフッ化物をカルシウム塩と反応させてフッ化カルシウムのような安定した固体に変換する方法があります。高温焼却では、高温炉でフッ化物を処理して無害化しますが、排ガス処理装置の設置により二次汚染を防ぐ必要があります。さらに、専用埋立地での廃棄では、漏出を防ぐためにライナーシステムやモニタリング装置が必須です。
なぜ人間が口に入れるものや、地球上の環境は、脱化学物質・ケミカルフリーであるべきなのか?
化学(ケミカル)物質とは、化石原料から作られる化合物のことです。化石原料とは、地球上の生き物や有機物などの物質が濃縮して石や油、ガスとなり、鉱物や石炭、レアメタルや石油など地球上で化石化し地底深くから採掘したものや、宇宙から降ってきた隕石に含まれる鉱物です。
化学とは化ける学問ともいう様に、これらの石や油やガスは化学反応を起こし、化け、燃えたり爆発したり素晴らしいエネルギーや生物を殺す殺菌作用や防腐作用、低コスト生産などを生み出すものですが、植物や生物、人間など環境には毒です。よって、人類の産業発展には必要なものですが、健康のためには使用量を減らしたり、より安全に環境にやさしい技術を開発したり、自然環境に気にしなくて良い宇宙での化学開発を進めることが、地球と人類の未来にとって良い選択と思われます。
地球上や近所では、限られた川や海の美しさを守るために、環境や健康を毒する化学物質は避けて、自然なケミカルフリーの安全なものを増やすこと、飲み水や空気や食べ物はケミカルフリーを保つことが、自分たちにとって心地よいものになると考えられます。
想像してみましょう。化石原料だらけで自然や生物がいない状況とは、火山の後の世界のようなものです。地底からマグマが化学反応で爆発し、植物や生物を焼き尽くし、水を蒸発させ、あたり一面は石に覆われた焼土です。地底で濃縮されていた毒を持つ危険な化学物質や化石原料もあり、すべての植物や生物を殺してしまいます。地球創生の焼土の地表や海水が安全になり生物が生まれるまでには何億年もかかりました。つまり地底で濃縮され落ち着いていた石油や鉱物を地上に掘り出すというのは、いまの地上の生き物には毒があるのです。よってこれ以上の地球の地底資源開発は、オゾン層の破壊をはじめ地上の人類にも存続影響を及ぼすレベルに来ていると考えられます。
一方、火山の後の世界とは宇宙の星に似ています。レアアース資源が豊富になり、オゾン層も空気も水もなく、放射能は地球上の数百倍、生物がいないので環境規制もありません。限りある緑の星の地上の自然を破壊してしまう地底資源開発はこの辺にしてもう少しで手に届く宇宙資源開発を早く進め、美しい地球上で人間が口に入れるものや地球上の生活環境は、脱化学物質・ケミカルフリーであるべきとするのが、21世紀の人類の健康や繁栄にとって賢い選択と考えられます。
フッ素に頼らなくても虫歯予防は出来る フッ素利用を開始した70年前までの伝統的で安全な人類の虫歯予防法は?
では古代からフッ素以前の70年前までの虫歯予防法は、どの様に行われたのでしょうか。以下に古代から70年前までの虫歯予防法について解説します。
1. 植物や自然素材を用いた方法
古代の人々は、自然界から得られるものを利用して歯を清潔に保とうとしました。
木の枝を使った歯磨き(チュウイッグ)
古代エジプトやインドでは、ミスワク(Miswak)やニームの枝が使われました。これらの枝には抗菌作用があり、歯を磨くことで虫歯の原因菌を抑える効果が期待されました。
薬草やハーブの利用
古代ローマやギリシャでは、ミントやセージを噛んだり煮出してうがいをすることで、口内を清潔に保ちました。アーユルヴェーダ(インド伝統医学)では、ニームの葉やクローブを噛むことで虫歯予防が行われました。
2. うがいの習慣
古代中国では、塩水でのうがいが広く行われていました。塩には抗菌作用があり、虫歯や歯周病予防に役立つとされました。日本でも、茶葉を煮出した液で口をすすぐ習慣があったと言われています。
3. 特定の食べ物の摂取
食事の工夫
古代では砂糖の摂取が少なく、自然食品が中心の食生活でした。これは虫歯リスクを減らしていました。古代エジプトやローマでは、チーズや乳製品を好んで食べることで、歯を強化していました(カルシウム補給)。
4. 灰や炭を使った歯磨き
古代ローマやギリシャでは、粉末状の骨や貝殻の灰を歯磨きの代用品として使いました。これらは研磨剤の役割を果たし、歯垢を除去しました。日本でも、木炭や焼いた卵の殻をすりつぶして歯磨きに使用する習慣がありました。
5. 噛むことで口腔ケア
硬い食材(穀物やナッツ類)をよく噛むことで、歯垢の付着を防ぎ、自然に歯を磨く効果がありました。現代と比べて加工食品が少ないため、硬い食材が歯のクリーニングに役立っていたと考えられます。
6. 宗教的・呪術的な予防
古代エジプトでは、虫歯は「虫」が原因と信じられており、お守りや呪文を使って虫を追い払う儀式が行われました。古代中国や日本でも、歯の健康を願うために寺院で祈りを捧げる文化がありました。
7. 古代日本の虫歯予防
日本では平安時代以前から、食事の後に口をすすぐ習慣がありました。江戸時代には、木の枝を加工した「歯木(はぎ)」が使われ、食事の後に歯をこすることで食べかすを取る習慣が広まりました。
砂糖が普及する、またフッ素を虫歯予防に使用開始した70年前までは、以上の様なオーラルケアで人類は発展を遂げてきました。
虫歯は甘く美味しい「糖分」摂取の副作用 虫歯菌と糖分をコントロールする安全なオーラルケアを
一方、甘く美味しい砂糖菓子が人類に広まった現代の慢性疾患ともいえる虫歯は、口腔内に存在する虫歯菌(S.ミュータンス菌)が「糖分」をエサに酸を産生し、その酸が歯のエナメル質を溶かすことで発生します。特に食品や飲料に含まれる精製糖などがこのプロセスを促進します。
虫歯菌は通常、口腔内の常在菌として存在し、口腔内フローラの一部として一定の役割を果たしています。しかし、精製された「糖分」を多量に摂取すると、虫歯菌が活性化し、大量の酸を産生。これがエナメル質を傷つけ、虫歯の原因となります。
虫歯リスクを高める食品と飲料
清涼飲料水
炭酸飲料やスポーツドリンクは、高濃度の糖分が虫歯菌のエサとなり、酸を産出しエナメル質を溶かします。
甘い菓子類
キャンディーやグミなどの粘着性の高いお菓子は、歯に長く付着し、虫歯菌が活動しやすい環境を作ります。
焼き菓子・スナック類
クッキーやクラッカーは、精製小麦粉と糖分が虫歯菌のエサとなります。
加工食品
ケーキや白パンは、大量の精製糖と小麦粉が含まれ、口腔内に糖分を供給します。
甘味飲料
果汁飲料や甘いミルクティーは、自然由来の果糖に加えて添加糖も多く含み、虫歯リスクを高めます。
その他
砂糖入りヨーグルトやアイスクリーム、ジャムも糖分が多く、長時間歯に残りやすい食品です。
成分表示名称は、
「フルクトース」、「ブドウ糖」、「果糖ブドウ糖液糖」、「ショ糖」、「砂糖」、「小麦粉」など。
虫歯予防には、以上の美味しいものを食べたり飲んだりした後には、口をゆすぎ歯を磨くことが大切です。また、ブラッシングの徹底や、飲み込んでも安全な抗菌剤を使用して口腔内フローラを整えることが効果的です。特に、オーラルピースのような自然由来の製品は、口内保湿や唾液の働きをサポートしながら、虫歯菌のコントロールに役立ちます。
大好きな甘いものの食後に、口に糖分や炭水化物を残さない歯磨き習慣で、虫歯のない健康な口腔環境が目指せます。薬品や化学物質に頼らず、適切なオーラルケアで、人間本来の口腔機能を守ることは、安心で我が子にとって賢い選択といえます。
=====
参考情報
虫歯予防のフッ素、子供のIQ低下で米規制へ。米国主要メディア報道 2024年 9月24日
https://oralpeace.com/news/news-news/33862
判決文:2024年9月24日
https://fluoridealert.org/wp-content/uploads/2024/09/Court-Ruling.pdf
米国国家毒性プログラム(NTP)フッ素曝露と神経発達および認知に関する科学的知見の現状に関する系統的レビュー: 2024年8月
https://ntp.niehs.nih.gov/publications/monographs/mgraph08
=================
===================================================
今後のアメリカでの最新動向を見守っていきましょう。
愛する人にはオーラルピース
*米国ニュースメディア等の情報ソースへのお問い合わせは、ご興味のある方が各自で行っていただけます様お願いいたします。
最近の投稿
- オーラルピースがJST「STI for SDGs」奨励賞を受賞 株式会社トライフ(横浜) オーラルケア製品・歯科界で初の快挙 2025年10月19日
- 【受験ドリル掲載】「地頭がみるみる良くなる発想力・思考力ドリル 」にオーラルピースが教材としてご紹介 2025年9月14日
- オーラルピースと他の類似品や後発コピー製品との違いについて 2025年8月12日
- オーラルピースの類似品を謳う製品との大きな違いは? 2025年8月12日
- ギフテッド児と歯磨き:特性に寄り添うオーラルケアの新しいかたち 才能を育む口腔ケアの新常識 だれも取り残さないインクルーシブな歯磨きジェル オーラルピース 2025年8月2日